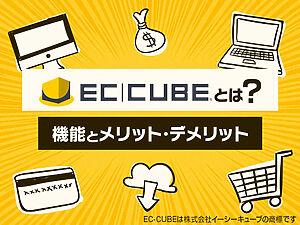EC-CUBE vs makeshop 特徴・機能・費用を徹底比較

ECサイトの構築を検討している方にとって、プラットフォーム選びは事業の成功を左右する重要な決断です。特に国内で人気の高いmakeshopとEC-CUBEは、それぞれ異なる特徴と強みを持っているため、どちらを選ぶべきか迷われる方も多いでしょう。本記事では、料金体系から機能面、カスタマイズ性まで7つの項目で詳しく比較し、あなたのビジネスに最適なプラットフォームを見つけるためのガイドをお届けします。初期費用を抑えたい方から、将来的な拡張性を重視する方まで、それぞれの目的に応じた選び方を具体的に解説していきます。
makeshopとEC-CUBE、どちらを選ぶべき?ECサイト構築で失敗しないための比較ガイド

ECサイト構築において、makeshopとEC-CUBEはどちらも魅力的な選択肢ですが、あなたのビジネス規模や技術的な要件によって最適解は大きく異なります。makeshopは手軽さとサポートの充実が魅力のASPカートサービスで、初心者でも簡単にECサイトを立ち上げられます。一方、EC-CUBEは自由度の高いカスタマイズが可能なオープンソースシステムで、独自性の高いサイト構築を実現できます。
最も重要なのは、現在の事業規模と将来のビジョンを明確にすることです。たとえば、個人事業主や小規模事業者が手軽にネットショップを始めたい場合、makeshopの月額制サービスは理想的な選択肢となります。実際に、makeshopでは月額1,100円から本格的なECサイトを運営でき、クレジットカード決済や在庫管理などの基本機能がすべて含まれています。
一方で、独自の機能やデザインにこだわりたい企業や、将来的に大規模な拡張を予定している場合は、EC-CUBEの方が適しているでしょう。EC-CUBEは無料で利用開始できるため初期コストを抑えられ、PHPの知識があれば思い通りのカスタマイズが可能です。ただし、サーバーの準備や保守管理は自社で行う必要があるため、技術的なリソースが必要になります。
比較の前に知っておきたい!makeshopとEC-CUBEの根本的な違い
makeshopとEC-CUBEを比較する前に、両者の根本的なサービス形態の違いを理解することが重要です。この違いを把握することで、あなたのビジネスにとってどちらがより適しているかを判断する基準が明確になります。
手軽さとサポートが魅力のASPカート「makeshop」
makeshopはASP(Application Service Provider)型のECカートサービスで、クラウド上で提供される完成されたシステムを月額料金で利用する形態です。このサービス形態の最大のメリットは、技術的な知識がなくても本格的なECサイトを構築できる点にあります。
具体的には、makeshopに申し込むだけで、サーバーの準備からセキュリティ対策、システムのアップデートまで、すべてをmakeshop側が代行してくれます。たとえば、アパレルショップを開業したい方の場合、商品の写真と説明文を用意すれば、最短1日でネットショップを開店できます。また、月額1,100円のフリーショッププランから11,000円のプレミアムショッププランまで、事業規模に応じた料金プランが用意されているため、スタートアップ企業でも無理なく導入できます。
さらに、makeshopでは専任のサポートスタッフによる手厚いサポートが提供されています。ECサイト運営で困ったことがあれば、電話やメールで気軽に相談でき、HTMLやCSSの知識がない方でも安心して利用できる環境が整っています。これは、自社でシステム管理者を雇う余裕がない中小企業にとって大きなメリットとなるでしょう。
自由なカスタマイズが可能なオープンソース「EC-CUBE」
EC-CUBEはオープンソースのECサイト構築システムで、ソースコードが無償で公開されており、自由にカスタマイズできることが最大の特徴です。この特徴により、他社との差別化を図りたい企業や、特殊な業務要件を持つ事業者にとって理想的な選択肢となっています。
オープンソースという性質上、初期費用は基本的に無料ですが、サーバーの準備やシステムの構築、保守管理はすべて自社で行う必要があります。たとえば、独自の会員制度や複雑な在庫管理システムを構築したい場合、EC-CUBEなら要件に合わせて自由に機能を追加できます。実際に、大手家具メーカーのニトリや化粧品ブランドのDHCなど、多くの企業がEC-CUBEをベースに独自のECサイトを構築しています。
ただし、PHPやMySQL、Webサーバーに関する技術的な知識が必要になるため、社内にエンジニアがいない場合は外部の開発会社に依頼する必要があります。開発費用は要件によって大きく異なりますが、基本的なカスタマイズでも50万円以上、本格的なシステム構築の場合は数百万円の予算を見込んでおく必要があるでしょう。
【7つの項目で徹底比較】makeshop vs EC-CUBE

makeshopとEC-CUBEの具体的な違いを明確にするため、ECサイト運営で重要な7つの項目について詳しく比較していきます。料金面から機能面まで、実際の運営コストや使い勝手を含めて解説します。
1. 料金プランの比較|初期費用・月額費用・手数料で見るトータルコスト
料金面での違いはmakeshopとEC-CUBE選択の最も重要な判断材料の一つです。両者は全く異なる料金体系を採用しているため、事業規模や売上予測に応じて慎重に検討する必要があります。
makeshopの料金体系は明確で分かりやすく、初期費用11,000円(税込)+ 月額1,100円~11,000円の定額制となっています。フリーショッププラン(月額1,100円)では商品数100個まで、ビジネスショッププラン(月額3,300円)では商品数1,000個まで、プレミアムショッププラン(月額11,000円)では商品数10,000個まで登録可能です。決済手数料は3.19%~3.49%で、売上に応じて支払う形になります。
たとえば、月商50万円のアパレルショップの場合、プレミアムショッププラン(月額11,000円)+ 決済手数料(約16,000円)で合計27,000円程度の運営コストとなります。この金額にはサーバー代、保守管理費、セキュリティ対策費がすべて含まれているため、追加コストを心配する必要がありません。
一方、EC-CUBEはライセンス費用は無料ですが、運営に必要な各種費用は別途発生します。レンタルサーバー代(月額3,000円~10,000円)、ドメイン代(年額1,000円~3,000円)、SSL証明書代(年額10,000円~50,000円)、システム保守費用(月額20,000円~100,000円)などが必要になります。さらに、カスタマイズ開発費用として初期に50万円~500万円の投資が必要な場合が多く、トータルコストはmakeshopを大幅に上回ることが一般的です。
2. 機能の比較|標準機能と拡張機能でできることの違い
ECサイト運営に必要な機能の充実度は、日々の業務効率に直結する重要な要素です。makeshopとEC-CUBEでは、標準で利用できる機能と拡張方法に大きな違いがあります。
makeshopは651種類の豊富な機能を標準搭載しており、ほとんどのECサイト運営に必要な機能が追加料金なしで利用できます。商品管理、受注管理、顧客管理、在庫管理などの基本機能はもちろん、クーポン発行、ポイント管理、メルマガ配信、アフィリエイト機能まで幅広くカバーしています。
具体的には、商品ページでは複数画像の掲載、商品オプション設定、関連商品表示が可能で、受注管理では注文ステータスの自動更新や配送業者との連携も標準で対応しています。決済方法も14種類(クレジットカード、コンビニ決済、銀行振込、代金引換、Amazon Pay、楽天ペイなど)から選択でき、顧客の利便性を高められます。
EC-CUBEの標準機能は必要最小限に絞られているのが特徴です。商品管理、受注管理、顧客管理、決済機能などの基本的な機能は搭載されていますが、より高度な機能は自社開発するか、有償のプラグインを購入する必要があります。たとえば、メルマガ配信機能は標準では含まれておらず、プラグイン(3万円~10万円)を購入するか、自社で開発する必要があります。
ただし、EC-CUBEの大きな優位性はカスタム機能の自由な追加が可能な点です。特殊な業務要件や独自のマーケティング施策に対応した機能を、制限なく開発できます。たとえば、B2B向けの複雑な価格体系や、製造業向けの特殊な在庫管理システムなど、業界特有のニーズにも柔軟に対応できるでしょう。
3. カスタマイズ性の比較|デザインと機能追加の自由度は?
サイトのデザインや機能をどこまで自由にカスタマイズできるかは、ブランディングや競合他社との差別化を図る上で重要な要素です。makeshopとEC-CUBEでは、カスタマイズのアプローチと自由度に大きな違いがあります。
makeshopでは173種類の無料テンプレートが用意されており、業種や好みに応じてデザインを選択できます。美容・コスメ、ファッション、食品、雑貨など、様々な業界に特化したプロ仕様のテンプレートが揃っています。HTMLとCSSの知識があれば、テンプレートをベースにしたカスタマイズも可能ですが、システムの根幹部分は変更できません。
たとえば、アパレルブランドがブランドイメージに合わせてカラーやフォントを変更したり、商品ページのレイアウトを調整したりすることは可能です。しかし、ショッピングカートの動作やチェックアウトフローなど、システムの核となる部分は既定の仕様に従う必要があります。これにより安定性は保たれますが、独自性の高い機能実装には限界があります。
EC-CUBEは完全にオープンソースであるため、技術的な制約はほとんどありません。デザインテンプレートは公式サイトで数十種類が提供されていますが、多くの企業は独自のデザインを一から作成しています。PHPとTwigテンプレートエンジンの知識があれば、サイトの外観から内部の動作まで、思い通りにカスタマイズできます。
実際の事例として、大手アパレル企業では商品の3D表示機能や、AIを活用したコーディネート提案機能をEC-CUBEベースで開発しています。また、B2B企業では顧客ごとに異なる価格表示や、複雑な承認フローを組み込んだ受注システムを構築するなど、業務要件に完全に特化したシステムを実現しています。
4. サポート体制の比較|困ったときに頼れるのはどっち?

ECサイト運営中にトラブルが発生した際のサポート体制は、事業継続性に直結する重要な要素です。makeshopとEC-CUBEでは、サポートの提供方法と充実度に明確な違いがあります。
makeshopは専任サポートスタッフによる手厚いサポートが大きな魅力です。平日10時から18時まで電話サポートが利用でき、技術的な質問からマーケティングのアドバイスまで幅広く対応してもらえます。メールサポートは24時間受付で、通常24時間以内に返信があります。
サポート内容も非常に実践的で、ECサイト運営の初心者でも安心して利用できるレベルです。たとえば、「商品登録の方法が分からない」「売上を伸ばすための施策を教えてほしい」「決済エラーの対処法を知りたい」といった様々な相談に、経験豊富なスタッフが丁寧に答えてくれます。また、定期的にECサイト運営に関するセミナーやウェビナーも開催されており、最新のトレンドや成功事例を学ぶ機会も提供されています。
さらに、makeshopではシステムの保守管理もすべて委託できるため、サーバーダウンやセキュリティ問題などの技術トラブルを心配する必要がありません。万が一障害が発生した場合も、makeshop側で迅速に対応してもらえるため、事業主は本業に集中できます。
EC-CUBEはオープンソースのため公式の有償サポートは基本的に提供されていません。ただし、コミュニティベースのサポートは充実しており、公式フォーラムやユーザーコミュニティで情報交換が行われています。技術的な知識があるユーザーにとっては、この環境は非常に有用です。
一方で、技術的な知識がない事業者にとっては、サポート面でのハードルが高いのが現実です。システムトラブルが発生した場合、自社で解決するか、外部の開発会社に依頼する必要があります。開発会社との保守契約を結ぶ場合、月額20万円~100万円程度の費用が発生することも珍しくありません。
5. セキュリティ面の比較|安心して運営するための違いとは
ECサイトでは顧客の個人情報やクレジットカード情報を扱うため、セキュリティ対策は極めて重要です。情報漏洩や不正アクセスが発生すれば、事業の存続に関わる大きな損失を被る可能性があります。makeshopとEC-CUBEでは、セキュリティ対策のアプローチに大きな違いがあります。
makeshopではPCI DSS(Payment Card Industry Data Security Standard)に準拠した高水準のセキュリティ対策が標準で提供されています。PCI DSSは、クレジットカード情報を取り扱う事業者が遵守すべき国際的なセキュリティ基準で、makeshopを利用するだけで自動的にこの基準をクリアできます。
具体的なセキュリティ対策として、SSL証明書の自動更新、定期的なセキュリティパッチの適用、不正アクセスの監視、DDoS攻撃対策などが24時間365日体制で行われています。事業者側で特別な対策を講じる必要がなく、セキュリティ専門知識がない方でも安心してECサイトを運営できる環境が整っています。
また、makeshopではISO27001(情報セキュリティマネジメントシステム)の認証も取得しており、企業レベルでの情報管理体制が確立されています。定期的な第三者監査も受けているため、セキュリティレベルの客観的な担保も得られています。
EC-CUBEではセキュリティ対策をすべて自社で実装・管理する必要があります。オープンソースという性質上、セキュリティホールが発見された場合は迅速にアップデートを適用する必要がありますが、この作業は利用者の責任で行わなければなりません。
技術的な知識があれば、EC-CUBEでも高いセキュリティレベルを実現できます。たとえば、WAF(Web Application Firewall)の導入、定期的な脆弱性診断の実施、ログ監視システムの構築などにより、makeshop以上のセキュリティ対策を講じることも可能です。しかし、これらの対策には専門知識と継続的な投資が必要で、年間数百万円の費用がかかることも珍しくありません。
6. 集客・マーケティング機能の比較|売上アップに繋がる機能は?

ECサイトの成功には優れた商品と使いやすいシステムだけでなく、効果的な集客・マーケティング機能が不可欠です。makeshopとEC-CUBEでは、マーケティング支援機能の内容と活用方法に違いがあります。
makeshopはSEO対策機能が充実しており、検索エンジンからの自然流入を増やすための様々な施策を簡単に実施できます。商品ページのタイトルタグやメタディスクリプションの個別設定、URL の最適化、サイトマップの自動生成などが標準機能として提供されています。また、Googleアナリティクスとの連携も簡単で、アクセス解析に基づいた改善施策を継続的に実行できます。
SNS連携機能も豊富で、Facebook、Twitter、Instagram、LINEなどの主要SNSとの連携が可能です。商品情報の自動投稿や、SNS経由の流入分析なども行えるため、現代的なオムニチャネル戦略を展開できます。
さらに、makeshopではメルマガ配信機能が標準搭載されており、顧客セグメントに応じた効果的なメールマーケティングが実施できます。購入履歴や閲覧履歴に基づいた自動配信設定も可能で、リピート購入の促進に効果を発揮します。実際に、makeshopを利用するアパレルショップでは、誕生日月のクーポン配信により平均購入単価が20%向上したという事例もあります。
EC-CUBEでは基本的なSEO機能は搭載されていますが、高度なマーケティング機能は自社開発するか、プラグインを導入する必要があります。ただし、この自由度の高さを活かして、業界特有のマーケティング手法や独自の顧客分析機能を実装することも可能です。
たとえば、大手化粧品メーカーでは、EC-CUBEベースで顧客の肌質診断結果と購入履歴を組み合わせたパーソナライズ機能を開発し、個別最適化されたレコメンド機能を実現しています。また、B2B企業では営業担当者別の売上管理や、地域別の販促施策効果測定など、高度なCRM機能を独自に構築している事例もあります。
7. スケーラビリティ(拡張性)の比較|事業の成長に対応できるか
事業の成長に伴うアクセス数の増加や機能追加の要求に、システムが柔軟に対応できるかどうかは、長期的な事業戦略において重要な判断材料です。makeshopとEC-CUBEでは、スケーラビリティのアプローチに根本的な違いがあります。
makeshopはクラウドベースのインフラストラクチャを採用しているため、アクセス数の急激な増加にも自動的に対応できます。通常時は効率的なリソース利用でコストを抑え、セール期間やテレビ放映後のアクセス集中時には自動的にサーバー能力を拡張する仕組みが整っています。
実際に、makeshopを利用するファッション通販サイトでは、テレビ番組で商品が紹介された際に通常の100倍のアクセスが集中しましたが、システムダウンすることなく注文を受け続けることができました。この際の追加費用は一切発生せず、機会損失を防ぐことができたのです。
ただし、makeshopではシステムの根幹部分をカスタマイズできないため、事業の成長に伴って特殊な要件が生じた場合、対応に限界があります。たとえば、複数の倉庫との在庫連携や、複雑な卸売価格体系など、標準機能でカバーできない要求には対応できません。
EC-CUBEは完全に自社管理のシステムであるため、理論上は無制限の拡張が可能です。事業規模の拡大に応じてサーバー構成を変更し、必要な機能を継続的に追加していくことができます。大手企業の中には、EC-CUBEを基盤として年商数百億円規模のECサイトを運営している事例もあります。
しかし、スケーラビリティを実現するためには継続的な技術投資が必要です。アクセス数の増加に対応するためのサーバー増強、データベースの最適化、CDN(Content Delivery Network)の導入など、成長段階に応じた様々な対策を自社で企画・実行する必要があります。これらの対策には専門的な知識と相当な予算が必要で、年間数千万円の投資が必要になる場合もあります。
結局どっちがいい?makeshopとEC-CUBEのメリット・デメリットまとめ
ここまでの詳細比較を踏まえて、makeshopとEC-CUBEそれぞれの明確なメリットとデメリットを整理していきます。どちらを選ぶべきかの判断材料として、実際の運営場面を想定した具体的な観点から解説します。
makeshopを選ぶメリット・デメリット
makeshopの最大のメリットは「手軽さ」と「安心感」にあります。ECサイト運営に必要なすべての機能が整ったパッケージを、月額定額制で利用できる点は、特に中小企業や個人事業主にとって大きな魅力です。
makeshopの主なメリットとして、まず初期投資の少なさが挙げられます。初期費用11,000円と月額1,100円から始められるため、リスクを最小限に抑えてECサイト運営をスタートできます。実際に、化粧品の個人輸入販売を始めた事業者の方は、「初月の売上が5万円程度だったので、makeshopの低コストは事業継続の決め手になった」と話しています。
技術的な知識が不要な点も大きなメリットです。HTMLやCSSを知らなくても、マウス操作だけで本格的なECサイトを構築でき、商品登録から受注管理まで直感的に操作できます。さらに、システムの保守管理やセキュリティ対策はすべてmakeshop側が担当するため、事業主は商品開発やマーケティングに集中できます。
充実したサポート体制も見逃せません。専任スタッフによる電話・メールサポートがあるため、困った時にすぐに相談できる安心感があります。ECサイト運営の初心者にとって、この心理的サポートは非常に価値があるでしょう。
一方で、makeshopのデメリットもあります。最も大きな制約はカスタマイズの自由度の低さです。デザインテンプレートを基にした変更は可能ですが、システムの根幹部分は変更できません。そのため、独自性の高い機能や、特殊な業務要件への対応には限界があります。
また、月額費用と決済手数料が継続的に発生するため、売上規模が大きくなると運営コストが割高になる可能性があります。月商1,000万円を超える規模になると、makeshopの手数料だけで月額30万円以上になることもあり、この段階では自社システムの構築を検討する企業も多くなります。
EC-CUBEを選ぶメリット・デメリット
EC-CUBEの最大のメリットは「自由度の高さ」と「コストパフォーマンス」です。オープンソースという特性を活かして、事業要件に完全に特化したECサイトを構築できる点は、他のプラットフォームでは実現できない大きな優位性です。
EC-CUBEの主なメリットとして、まずライセンス費用が無料である点が挙げられます。初期のシステム導入コストを大幅に抑えることができ、浮いた予算をマーケティングや商品開発に投入できます。実際に、スタートアップのファッションブランドでは、EC-CUBEを選択することで初期費用を300万円節約し、その資金をインフルエンサーマーケティングに活用して大きな成功を収めました。
完全なカスタマイズ性も大きな魅力です。PHPの知識があれば、思い通りの機能を制限なく実装できます。たとえば、製造業のB2B企業では、顧客ごとに異なる価格体系や複雑な承認フローを組み込んだ独自のシステムを構築し、業務効率を大幅に向上させています。また、アパレル企業では3D商品表示機能やAIによるコーディネート提案機能を実装し、他社との明確な差別化を実現しています。
スケーラビリティの面でも、事業の成長に応じて柔軟にシステムを拡張できます。小規模な共用サーバーから始めて、アクセス数の増加に応じて専用サーバーやクラウドサービスへと段階的に移行することで、常に最適なコストパフォーマンスを維持できます。大手企業の事例では、EC-CUBEベースで年商100億円を超えるECサイトを運営している例もあります。
しかし、EC-CUBEにも明確なデメリットがあります。最も大きな課題は技術的な専門知識の必要性です。システムの構築から運用まで、PHPやデータベース、サーバー管理に関する深い知識が必要になります。社内にエンジニアがいない場合は、外部の開発会社に依頼する必要があり、開発費用として数百万円から数千万円の投資が必要になることも珍しくありません。
運用面での負担も大きなデメリットです。セキュリティ対策、システムアップデート、サーバー管理をすべて自社で行う必要があり、これらの作業には継続的な時間と費用が必要です。セキュリティホールが発見された場合の緊急対応や、アクセス集中時のサーバー増強など、24時間365日の監視体制を整える必要もあります。
【目的別】あなたにおすすめなのはどっち?最適なプラットフォームの選び方

これまでの比較分析を踏まえて、具体的な事業状況や目的に応じた最適な選択を明確にしていきます。あなたのビジネスの現状と将来展望を以下のケースと照らし合わせて、最適なプラットフォームを見つけてください。
こんな方にはmakeshopがおすすめ!3つのケース
makeshopが最適な選択となるのは、手軽さと安定性を重視し、標準的なECサイト機能で事業目標を達成できる場合です。以下の3つのケースに当てはまる方には、makeshopを強くおすすめします。
ケース1:ECサイト運営が初めて、または技術的な知識が限られている場合
個人事業主や小規模事業者で、ECサイト運営の経験が浅い方にとって、makeshopは理想的な選択肢です。たとえば、これまで実店舗だけで営業していたアクセサリー販売店が、コロナ禍をきっかけにオンライン販売を始める場合を考えてみましょう。HTMLやCSS、サーバー管理の知識がなくても、商品写真と説明文を用意するだけで本格的なECサイトを構築できます。
実際の事例として、手作り石鹸を販売する個人事業主の方は、「パソコンは基本操作しかできない状態でしたが、makeshopなら1週間でネットショップを開店できました。最初の月から10万円の売上を達成し、今では月商50万円まで成長しています」と話しています。専任サポートスタッフが丁寧に操作方法を教えてくれるため、技術的な不安を感じることなくECサイト運営に集中できるのです。
ケース2:初期投資を抑えて、リスクを最小限にしたい場合
新規事業の立ち上げや、既存事業のテスト的なオンライン展開を検討している場合、makeshopの低い初期費用は大きなメリットとなります。初期費用11,000円と月額1,100円から始められるため、市場の反応を見ながら段階的に投資を増やすことができます。
具体的には、地方の特産品を全国販売したい農業法人が、まずは小規模でオンライン販売をテストする場合などが該当します。「いきなり数百万円をかけてシステムを作るのはリスクが高すぎる。makeshopなら月1万円程度で始められるので、売上の見通しが立ってから本格的な投資を検討できる」という判断は非常に合理的です。売上が伸びない場合でも、損失を最小限に抑えられる安心感があります。
ケース3:本業に集中したく、システム管理に時間をかけたくない場合
経営者として本業の商品開発やマーケティングに注力したい方にとって、makeshopの「おまかせ運営」は非常に価値があります。サーバー管理、セキュリティ対策、システムアップデートなどの技術的な作業をすべて委託できるため、ECサイト運営以外の重要な業務に時間を使えます。
美容サロンを経営しながら化粧品のオンライン販売を行っている事業者の例では、「サロンの接客とECサイトの管理を両立するのは現実的ではありませんでした。makeshopにしてからは、システムトラブルを心配することなく、お客様への施術と商品企画に専念できています」とのことです。月額費用は経費として計上でき、その分の時間を売上向上につながる活動に投入できるため、結果的に高いROI(投資収益率)を実現できています。
こんな方にはEC-CUBEがおすすめ!3つのケース
EC-CUBEが最適となるのは、独自性や拡張性を重視し、技術的なリソースを確保できる場合です。以下の3つのケースに該当する方には、EC-CUBEの導入を検討することをおすすめします。
ケース1:独自の機能やデザインで競合他社と差別化したい場合
既存のECサイトでは実現できない独自の顧客体験を提供したい企業にとって、EC-CUBEの自由度は大きな武器となります。たとえば、オーダーメイド商品を扱う企業が、顧客の要望をリアルタイムで3D表示する機能を実装したい場合、標準的なECプラットフォームでは対応できません。
実際の事例として、高級家具メーカーでは、EC-CUBEベースで顧客が部屋の写真をアップロードすると、AI が最適な家具配置を提案する機能を開発しました。この独自機能により、競合他社との明確な差別化を実現し、平均購入単価が30%向上しています。「単に商品を売るだけでなく、お客様の暮らしをトータルでサポートする体験を提供できるようになりました」と担当者は話しています。
ケース2:既存の業務システムとの高度な連携が必要な場合
製造業や卸売業など、複雑な業務フローを持つ企業では、ECサイトと既存システムとの密接な連携が必要になります。在庫管理システム、会計システム、CRMシステムなどとのリアルタイム連携を実現するには、システムの内部構造を自由にカスタマイズできるEC-CUBEが適しています。
大手部品メーカーの事例では、全国の営業所の在庫情報をリアルタイムで統合し、顧客が注文した際に最も効率的な配送ルートを自動計算する機能をEC-CUBEで実装しました。この統合システムにより、配送コストを20%削減し、納期も平均2日短縮できています。「既存の基幹システムとの完全な連携により、人的ミスを大幅に削減し、業務効率が飛躍的に向上しました」とシステム担当者は評価しています。
ケース3:将来的に大規模な展開を予定しており、長期的なコストパフォーマンスを重視する場合
年商数億円規模への成長を見据えている企業や、複数ブランドでの展開を計画している場合、長期的な視点でのコストパフォーマンスを考慮するとEC-CUBEが有利になります。初期投資は必要ですが、売上規模の拡大に伴う手数料負担がないため、事業が成長するほど経済的メリットが大きくなります。
アパレルブランドを展開する企業では、最初は1ブランドでEC-CUBEを導入し、その後5年間で10ブランドまで拡張しました。各ブランドで共通のシステム基盤を活用しながら、ブランドごとの独自性も保持できています。「makeshopで10ブランドを運営すれば月額100万円以上の費用がかかりますが、EC-CUBEなら同じサーバーで複数サイトを運営できるため、大幅なコスト削減を実現できています」と経営陣は説明しています。
まとめ:自社の目的と将来像に合ったプラットフォーム選びが成功の鍵

makeshopとEC-CUBEの比較を通じて明らかになったのは、どちらも優れたプラットフォームであり、選択の決め手は事業の性質と将来のビジョンにあるということです。最適な選択をするためには、現在の事業状況と中長期的な展望を整理し、それぞれのプラットフォームの特性と照らし合わせることが重要です。
makeshopは「手軽さ」「安定性」「サポートの充実」が最大の魅力です。ECサイト運営の初心者や、技術的なリソースが限られている中小企業にとって、理想的な選択肢となるでしょう。月額1,100円から始められる低い初期投資と、专任スタッフによる手厚いサポートにより、リスクを最小限に抑えてECサイト運営をスタートできます。また、651種類の豊富な標準機能により、ほとんどの一般的なECサイト運営ニーズに対応可能です。
一方、EC-CUBEは「自由度」「拡張性」「コストパフォーマンス」において優位性があります。独自の機能やデザインで競合他社との差別化を図りたい企業や、複雑な業務要件を持つ企業にとって、制限のないカスタマイズ性は大きな武器となります。また、売上規模が拡大するほど経済的メリットが大きくなるため、将来的な成長を見据えた投資として捉えることができます。
重要なのは、現在の制約条件だけでなく、3年後、5年後のビジネス展開を見据えた判断をすることです。たとえば、現在は小規模でもIPO を目指している企業であれば、将来の拡張性を考慮してEC-CUBEを選択することが戦略的に正しい場合もあります。逆に、安定した収益基盤を築くことを優先する企業であれば、makeshopの安定性とサポート体制を活用する方が適しているでしょう。
最終的には、「何を優先するか」を明確にすることが成功への第一歩です。手軽さと安心感を重視するならmakeshop、独自性と拡張性を追求するならEC-CUBEという基本方針を軸に、あなたのビジネスに最適なプラットフォームを選択してください。どちらを選んだとしても、顧客のニーズに応える優れた商品とサービスを提供することが、ECサイト成功の根本的な要因であることを忘れずに、着実な事業成長を目指していきましょう。
100%プライバシーを保証いたします