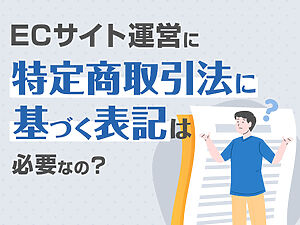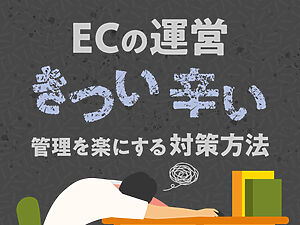ネットショップ送料の決め方!設定パターンと安く抑えるコツ
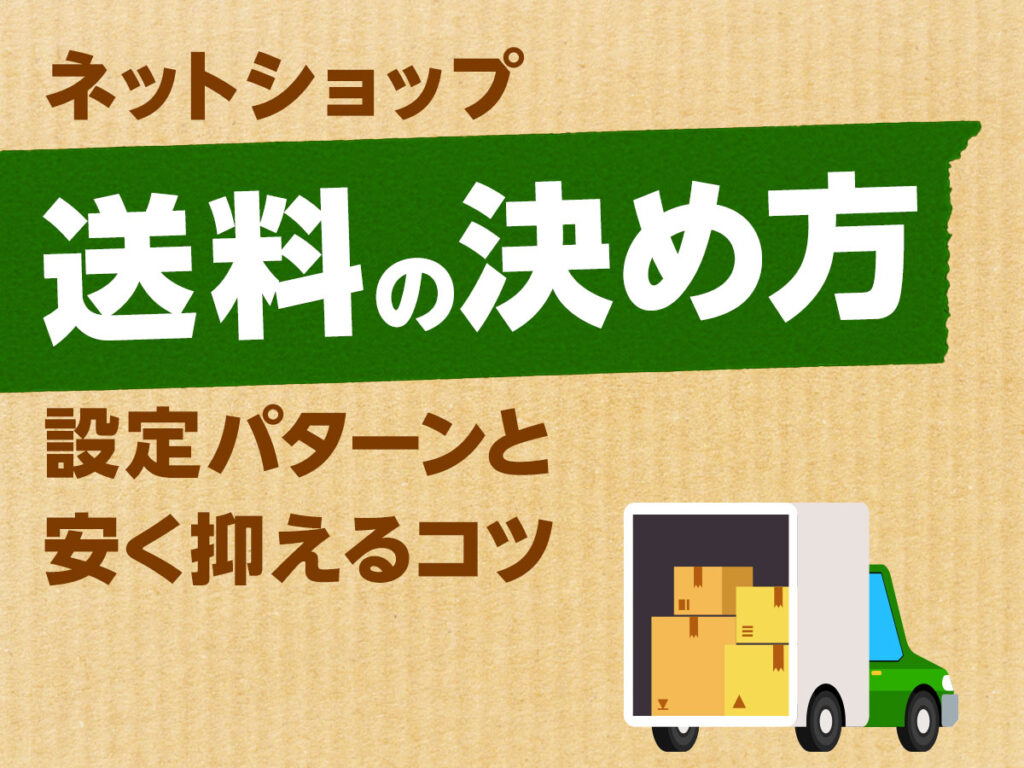
ネットショップの運営において、送料設定は顧客の購買決定に大きな影響を与える重要な要素です。送料が高すぎれば購入を諦められ、安すぎれば利益を圧迫してしまいます。本記事では、ECサイト運営者が抱える「送料をいくらに設定すべきか」「どうすれば送料を抑えながら利益を確保できるか」といった悩みに対して、具体的な解決策をご提案します。送料設定の基本から7つのパターン別比較、さらにコスト削減のコツまで、実践的な内容を詳しく解説していきます。適切な送料設定により、顧客満足度と収益性の両立を実現し、あなたのECサイトの売上向上につなげましょう。
ECサイトの送料設定は売上を左右する重要ポイント|最適な決め方を徹底解説

ECサイトにおける送料設定は、単なるコスト項目ではなく売上に直結する重要な戦略要素です。ここでは送料設定が顧客行動に与える影響と、最適な設定方法の基本的な考え方について解説します。
送料設定が顧客の購買行動に与える影響は想像以上に大きく、多くの消費者が送料を含めた総額で購入判断を行っているのが現実です。実際に、送料が予想より高かったことを理由にカート離脱する顧客は全体の約70%にも上るという調査結果があります。これは、商品価格がいくら魅力的でも、送料次第で売上が大きく左右されることを意味しています。
たとえば、同じ商品を販売する2つのショップがあったとします。Aショップは商品価格3,000円で送料800円、Bショップは商品価格3,500円で送料無料とした場合、総額は前者が3,800円、後者が3,500円となります。この場合、多くの顧客は送料無料のBショップを選ぶ傾向があります。なぜなら、消費者心理として「送料」は追加コストと感じられ、同じ総額でも送料がかかる方が損をした気分になるからです。
一方で、送料設定は事業の収益性にも直結します。送料を安く設定しすぎると物流コストが事業を圧迫し、継続的な運営が困難になってしまいます。特に小さな商品や軽い商品を扱うショップでは、実際の配送費に対して送料が安すぎると赤字の原因となります。逆に、送料を高く設定しすぎると競合他社に顧客を奪われるリスクが高まります。
最適な送料設定を実現するためには、自社の商品特性、配送エリア、競合状況、そして顧客のニーズを総合的に分析する必要があります。また、送料設定は一度決めたら終わりではなく、売上データや顧客の反応を見ながら継続的に改善していくことが重要です。効果的な送料設定により、顧客満足度を保ちながら適正な利益を確保し、持続可能なECサイト運営を実現できるのです。
まずは基本から!通販サイトにおける送料の考え方と相場
送料設定を適切に行うためには、まず送料がどのような仕組みで決まるのか、そして市場での一般的な相場はどの程度なのかを理解する必要があります。ここでは送料の基本的な考え方と現在の相場について詳しく説明します。
通販の送料はどのように決まる?基本的な仕組みを理解しよう
通販における送料は、主に配送業者の料金体系に基づいて決定されます。配送料金は「荷物のサイズ」「重量」「配送距離」「配送オプション」の4つの要素によって決まるのが一般的です。これらの要素を理解することで、自社に最適な送料設定の基礎を築くことができます。
荷物のサイズについては、縦・横・高さの3辺の合計で料金区分が決まります。たとえば、ヤマト運輸の宅急便では60サイズ(3辺計60cm以内)から200サイズ(3辺計200cm以内)まで段階的に料金が設定されています。同じ商品でも梱包方法によってサイズが変わるため、効率的な梱包により送料を抑えることが可能です。具体的には、不要な空間を減らしたり、薄型の梱包材を選んだりすることで、一回り小さいサイズ区分に収めることができます。
重量についても、サイズと同様に段階的な料金設定がされています。重量による料金区分は、軽いものから重いものまで幅広く設定されており、商品の性質によって大きく影響します。たとえば、書籍のように小さくても重い商品と、衣類のように大きくても軽い商品では、配送料金の決定要因が異なります。
配送距離は、発送元から配送先までの地理的な距離によって決まります。一般的に同一都道府県内が最も安く、離島や遠隔地になるほど料金が高くなります。これは、配送にかかる時間とコストが距離に比例するためです。全国に顧客がいるECサイトでは、この地域差をどう吸収するかが送料設定の重要なポイントとなります。
配送オプションとしては、時間指定配送、代金引換、保険付きサービスなどがあり、これらを利用すると基本料金に追加料金が発生します。顧客サービスを向上させるためにこれらのオプションを提供する場合は、その分のコストも送料設定に反映させる必要があります。
ネットショップの送料、平均や相場はいくら?
現在のネットショップにおける送料の相場を理解することは、競争力のある価格設定を行う上で非常に重要です。2024年の調査によると、ECサイトの平均送料は全国一律で500円から800円程度となっており、商品カテゴリーや事業規模によって幅があります。
小型商品を扱うショップの場合、送料相場は300円から600円程度が一般的です。たとえば、アクセサリーや化粧品、書籍などの軽量商品を扱うショップでは、メール便やネコポスなどの小型配送サービスを利用することで、比較的安い送料設定が可能です。実際に、楽天市場やAmazonマーケットプレイスでも、小型商品の送料は300円から500円程度に設定されているショップが多く見られます。
中型商品を扱うショップでは、送料相場は500円から900円程度となります。家電製品や食品、衣類などがこのカテゴリーに該当し、標準的な宅配便サービスを利用するため、サイズと重量のバランスによって料金が決まります。特に食品系のECサイトでは、冷蔵・冷凍配送の必要があるため、通常の宅配便よりも200円から300円程度高い送料設定になることが一般的です。
大型商品や家具類を扱うショップの場合、送料は1,000円から3,000円、場合によってはそれ以上となることもあります。これらの商品は特別な配送サービスや設置サービスが必要になることが多く、配送業者との個別契約によって料金が決定されることが一般的です。
**送料無料を実施しているショップは全体の約40%**を占めており、特に大手ECサイトではこの傾向が顕著です。ただし、送料無料の場合でも、実際には商品価格に送料分が含まれているケースがほとんどです。たとえば、送料800円を商品価格に上乗せして「送料無料」として販売している場合、実質的には顧客が送料を負担していることになります。このような価格設定は、顧客の心理的な購入ハードルを下げる効果がある一方で、小額商品の場合は商品価格が割高に見えるデメリットもあります。
利益と顧客満足度を両立!ECサイトの送料を決める5つのステップ
適切な送料設定を行うためには、体系的なアプローチが必要です。ここでは、利益確保と顧客満足度の両立を実現するための具体的な5つのステップを詳しく解説します。
ステップ1:配送を依頼する業者を選ぶ

送料設定の第一歩は、信頼できる配送業者を選定することです。配送業者の選択は送料だけでなく、配送品質や顧客満足度にも大きく影響するため、慎重に検討する必要があります。主要な配送業者にはヤマト運輸、佐川急便、日本郵便があり、それぞれ異なる特徴と料金体系を持っています。
ヤマト運輸の宅急便は、配送品質の高さと全国をカバーする配送網で知られています。特に個人向けの配送サービスに定評があり、時間指定や再配達サービスが充実しています。料金は他社と比較してやや高めですが、顧客満足度を重視するECサイトには適した選択肢といえます。たとえば、高級品や壊れやすい商品を扱うショップでは、配送事故のリスクを最小限に抑えられるヤマト運輸を選ぶことが多いです。
佐川急便は、法人向けのサービスに強みを持ち、大口契約での料金交渉に応じやすい特徴があります。特に重量のある商品や大型商品の配送では、他社よりも競争力のある料金を提示することが多いです。BtoB向けのECサイトや、業務用商品を扱うショップにとって有力な選択肢となります。
日本郵便は、レターパックやクリックポストなど、小型軽量商品に適したサービスが豊富です。特に全国一律料金のサービスが多く、地域格差を気にせずに送料設定ができるメリットがあります。書籍や化粧品サンプル、アクセサリーなどの小型商品を扱うショップでは、コスト効率の良い配送が実現できます。
配送業者を選定する際は、料金だけでなく配送エリア、配送日数、追跡サービスの有無、保険制度、顧客対応の質なども総合的に評価することが重要です。また、複数の業者と契約して商品や配送先に応じて使い分けることで、コスト最適化と顧客満足度向上の両立が可能になります。
ステップ2:自社で取り扱う商品のサイズと重量を把握する

正確な送料設定を行うためには、取り扱う商品の物理的特性を詳細に把握することが不可欠です。商品のサイズと重量は配送料金の主要な決定要因であり、この情報が不正確だと適切な送料設定ができません。
商品サイズの測定では、梱包後のサイズを基準にする必要があります。商品単体のサイズではなく、緩衝材や梱包材を含めた最終的な荷物のサイズが配送料金に影響するからです。たとえば、10cm×10cm×3cmの商品でも、適切な保護のために20cm×15cm×8cmの箱に梱包する必要がある場合、料金計算は後者のサイズで行われます。効率的な梱包設計により、配送サイズを最小限に抑えることで送料コストを削減できるのです。
重量についても、梱包材を含めた総重量を正確に測定することが重要です。軽い商品でも梱包材によって重量が大幅に増加することがあります。特に壊れやすい商品の場合、十分な緩衝材が必要になるため、商品重量の2倍から3倍の総重量になることも珍しくありません。
商品バリエーションが多い場合は、代表的な商品をカテゴリー別に分類し、それぞれの標準的なサイズと重量を設定することが効率的です。たとえば、アパレルショップの場合、「Tシャツ1枚」「厚手のセーター1枚」「ジーンズ1本」といった具合に商品タイプ別の基準を設定し、複数購入時の組み合わせパターンも想定しておきます。
また、季節商品や限定商品など、通常と異なるサイズ・重量の商品がある場合は、事前に配送テストを行うことをお勧めします。実際に梱包して配送業者に料金を確認することで、想定外のコスト増加を防ぐことができます。
ステップ3:発送元から主要な届け先までの実費を試算する
配送実費の正確な把握は、利益を確保しながら競争力のある送料設定を行うための基本となります。主要な配送先への実費を詳細に試算することで、地域別の送料格差や採算性を正確に評価できます。
まず、自社の顧客データを分析して主要な配送先を特定します。多くのECサイトでは、首都圏、関西圏、中部圏の3大都市圏が配送先の大部分を占めますが、商品特性や顧客層によって地域分布は大きく異なります。たとえば、地方特産品を扱うショップでは都市部への配送が中心となり、農業資材を扱うショップでは地方部への配送が多くなります。
実費試算では、代表的な商品について各配送先への料金を具体的に調べます。ヤマト運輸の場合、東京から大阪への60サイズ荷物は970円、東京から福岡への同サイズ荷物は1,350円といった具合に、距離に応じて料金が変動します。この地域差を送料設定にどう反映させるかが重要なポイントとなります。
複数購入時の配送費についても詳細に検討する必要があります。商品を複数購入された場合、同梱可能であれば配送費は1回分で済みますが、サイズや重量の制限により複数口配送になる場合もあります。たとえば、書籍を5冊購入された場合、重量制限により2口に分けて配送する必要があるかもしれません。このような場合の配送費負担をどうするかも事前に決めておく必要があります。
特別な配送サービスが必要な商品についても実費を確認します。冷蔵・冷凍商品、危険物、大型商品などは通常の宅配便とは異なる料金体系となるため、個別に確認が必要です。また、時間指定や代金引換などのオプションサービスを利用する場合の追加料金も含めて試算します。
これらの実費データを基に、全国平均での配送費を算出し、それを基準として送料設定を検討します。地域による配送費の差が大きい場合は、全国一律料金にするか地域別料金にするかを慎重に判断する必要があります。
ステップ4:競合他社の送料設定をリサーチする
市場における競争力を維持するためには、競合他社の送料設定を詳細に調査し、自社のポジショニングを明確にすることが重要です。競合分析により、適切な価格帯の設定と差別化ポイントの発見が可能になります。
競合調査では、直接的な競合だけでなく、同じ商品カテゴリーを扱う大手ECサイトも調査対象に含めることが重要です。たとえば、ハンドメイドアクセサリーを販売する場合、同様の個人ショップだけでなく、楽天市場やminneなどのプラットフォーム内のショップも競合として分析します。大手プラットフォームでは送料無料のショップが多いため、その対抗策も検討する必要があります。
調査項目としては、基本送料、送料無料の条件、地域別料金の有無、配送オプションの種類と料金、複数購入時の取り扱いなどを体系的に整理します。特に送料無料の実施条件は詳細に調査し、自社での実現可能性を検討します。たとえば、競合が「5,000円以上購入で送料無料」を実施している場合、自社の平均客単価や利益率と照らし合わせて同様の条件設定が可能かを分析します。
価格以外の差別化要素についても注目します。配送スピード、梱包の丁寧さ、追跡サービスの提供状況、配送事故時の対応など、顧客が重視する配送サービスの品質面での比較も行います。料金が多少高くても、サービス品質で差別化できれば競争力を維持できる場合があります。
競合の送料設定変更についても継続的に監視することが重要です。特に繁忙期やキャンペーン期間中は送料設定を変更するショップが多いため、定期的なチェックが必要です。また、新規参入者の動向も把握し、市場全体のトレンドを理解することで、適切なタイミングでの送料見直しが可能になります。
ステップ5:自社に合った送料設定のパターンを決定する
これまでのステップで収集した情報を基に、自社のビジネスモデルと顧客ニーズに最適な送料設定パターンを選択します。送料設定は事業戦略の一部であり、短期的な売上だけでなく長期的な顧客関係構築も考慮して決定する必要があります。
自社の商品特性を踏まえた設定が重要です。高単価商品を扱うショップでは送料の負担感が相対的に小さいため、実費に近い送料設定でも顧客に受け入れられやすいです。逆に、低単価商品を扱うショップでは送料の割合が大きくなるため、送料無料や低額設定を検討する必要があります。たとえば、500円の商品に800円の送料では明らかにバランスが悪く、顧客の購買意欲を大きく削ぐことになります。
顧客の購買パターンも重要な判断材料です。リピート購入が多い顧客層では、初回購入時の送料よりも継続的な利便性を重視する傾向があります。この場合、年会費制の送料無料サービスや、会員ランクに応じた送料優遇制度なども選択肢となります。一方、単発購入が中心の商品では、初回購入時の送料設定が最も重要になります。
事業規模と成長段階も送料設定に影響します。スタートアップ期では顧客獲得を優先して送料を抑えた設定にし、事業が安定してから適正化を図ることも戦略の一つです。ただし、後から送料を上げることは顧客の反発を招く可能性があるため、将来的な収益性も考慮した慎重な判断が必要です。
最終的には、複数のパターンでテスト運用を行い、売上データと顧客フィードバックを基に最適な設定を見つけることをお勧めします。A/Bテストにより異なる送料設定での顧客反応を比較し、データに基づいた意思決定を行うことで、最も効果的な送料設定を実現できます。
【徹底比較】ネットショップの送料設定7パターン|メリット・デメリットも解説
ネットショップの送料設定には複数のパターンがあり、それぞれに特徴とメリット・デメリットが存在します。ここでは代表的な7つのパターンについて、具体例を交えながら詳しく比較解説します。自社の事業特性に最適なパターンを見つけるための参考としてください。
パターン1:全国一律送料
全国一律送料は、配送先がどこであっても同じ送料を設定するパターンです。シンプルで分かりやすく、顧客にとって最も理解しやすい料金体系として多くのECサイトで採用されています。
このパターンの最大のメリットは、顧客の地域による不公平感を軽減できることです。遠方の顧客も都市部の顧客と同じ送料で購入できるため、全国に均等に顧客基盤を拡大したい事業者にとって有効な戦略となります。たとえば、北海道の顧客が九州のショップから商品を購入する場合でも、東京の顧客と同じ送料600円で済むため、地理的なハンディキャップを感じることなく購入できます。
運営面でのメリットも大きく、送料計算が簡単で顧客対応や受注処理の効率化が図れます。地域別の送料表を作成する必要がなく、顧客からの送料に関する問い合わせも減少します。また、ショッピングカートシステムの設定も簡単で、システム導入コストを抑えることができます。
一方で、デメリットとしては配送コストの地域差を適切に反映できないことが挙げられます。実際の配送費は近距離と遠距離で2倍以上の差があることも珍しくないため、全国一律料金では近距離顧客に配送費を多く負担させるか、遠距離顧客の配送費を事業者が負担することになります。たとえば、東京発の配送で関東圏内なら750円、沖縄なら1,400円の実費がかかる場合、一律900円に設定すると関東圏の顧客が150円多く負担し、沖縄の顧客は500円分を事業者が負担することになります。
このパターンは、配送費の地域差が小さい小型軽量商品や、全国展開を重視するブランドに適しています。また、顧客単価が高く送料の占める割合が小さい商品でも有効です。
パターン2:地域別送料
地域別送料は、配送先の地域に応じて異なる送料を設定するパターンです。実際の配送コストに基づいた公平な料金設定が可能で、事業者の収益性と顧客の公平感を両立できる設定方法です。
このパターンの大きなメリットは、配送実費に応じた適正な送料設定ができることです。近距離の顧客には安い送料を、遠距離の顧客には相応の送料を設定することで、どの地域への配送でも適正な利益を確保できます。たとえば、大阪から発送する場合、関西圏550円、関東圏650円、九州750円、北海道・沖縄900円といった設定により、距離に応じた公平な負担を実現できます。
事業戦略の観点では、地域別の価格設定により市場開拓の優先順位を明確にできるメリットもあります。主力市場である近距離エリアでは競争力のある送料を設定し、新規開拓したい遠距離エリアでは戦略的に送料を下げることも可能です。また、配送業者との契約で地域別割引が適用される場合、その恩恵を顧客に還元することもできます。
デメリットとしては、料金体系が複雑になり顧客に分かりにくくなることが挙げられます。特に遠距離地域の顧客にとっては送料が高く感じられ、購入を諦める原因となる可能性があります。北海道や沖縄、離島の顧客からは「送料が高すぎる」という不満が寄せられることも多く、顧客対応の負担が増加する場合があります。
また、システム面では地域判定機能が必要となり、ショッピングカートシステムの設定が複雑になります。郵便番号による自動判定システムの導入や、地域別送料表の作成・更新作業も必要になります。
このパターンは、重量のある商品や大型商品を扱うショップ、配送コストの地域差が大きい商品に適しています。また、特定地域に顧客が集中している場合も効果的です。
パターン3:商品・重量別の個別送料
商品や重量に応じて個別に送料を設定するパターンです。商品特性に最も適した配送方法と料金を選択できるため、配送効率の最大化と顧客満足度の向上を両立できます。
このパターンの最大のメリットは、商品に最適な配送サービスを選択できることです。小型商品にはメール便、重量商品には標準宅配便、冷蔵商品にはクール便といった具合に、商品特性に応じた最適な配送方法を選択し、それぞれに適正な送料を設定できます。たとえば、書籍なら200円のクリックポスト、家電なら800円の宅急便、生鮮食品なら1,200円のクール便といった設定が可能です。
顧客にとっても、購入する商品に応じた合理的な送料設定により納得感が得られます。軽い商品には安い送料、重い商品には相応の送料という設定は、顧客の常識的な感覚と一致するため受け入れられやすいです。また、商品ごとに配送オプションを選択できる場合、顧客のニーズに応じたサービス提供が可能になります。
事業面では、配送コストの最適化により利益率の向上が期待できます。それぞれの商品に最も効率的な配送方法を選択することで、総配送コストを削減できます。また、商品別の配送実績データを蓄積することで、より精密な原価管理が可能になります。
一方で、デメリットとしては管理の複雑さが挙げられます。商品数が多い場合、それぞれの送料設定と更新作業が膨大になり、運営負荷が大幅に増加します。また、顧客にとっても商品ごとに送料が異なるため、購入前に送料を確認する手間が発生し、場合によっては購入を躊躇する要因となる可能性があります。
さらに、複数商品を同時購入する場合の送料計算が複雑になります。異なる配送方法が必要な商品を一緒に購入された場合、同梱可能かどうかの判定や、複数口配送時の送料設定など、システム的にも運営的にも高度な対応が必要になります。
このパターンは、多様な商品カテゴリーを扱う総合ECサイトや、商品特性が大きく異なるアイテムを販売するショップに適しています。特に、配送方法によってコストが大きく変わる商品構成の場合に効果的です。
パターン4:購入金額別の送料
購入金額に応じて送料を段階的に設定するパターンです。顧客の購入金額を増やすインセンティブを提供しながら、適正な配送コストを回収できるバランスの取れた設定方法として人気があります。
このパターンの最大のメリットは、客単価向上効果が期待できることです。「あと少し購入すれば送料が安くなる」という心理的効果により、顧客により多くの商品を購入してもらうことができます。たとえば、「3,000円未満:送料800円、3,000円以上5,000円未満:送料400円、5,000円以上:送料無料」という設定では、2,800円の商品を検討している顧客が、送料を節約するために追加で300円以上の商品を購入する可能性が高くなります。
事業収益の観点では、高額購入者の配送コスト負担を軽減することで顧客満足度を向上させながら、低額購入者からは適正な配送費を回収できるメリットがあります。高額購入者は事業者にとって重要な顧客であり、配送サービスで優遇することで継続的な関係構築が可能になります。
また、在庫回転率の向上効果も期待できます。顧客がまとめ買いをすることで、一度の配送で複数商品を販売でき、在庫管理や配送効率の面でもメリットがあります。特に季節商品や期間限定商品の場合、この効果は顕著に現れます。
デメリットとしては、低額購入者にとって送料負担が重くなることが挙げられます。必要な商品だけを購入したい顧客にとっては、無理なまとめ買いを強要されているように感じられ、顧客体験を損なう可能性があります。特に単価の高い商品を扱う場合、送料無料のハードルが高すぎて現実的でないケースもあります。
また、送料無料の条件設定が不適切だと、利益を圧迫するリスクがあります。送料無料条件を低く設定しすぎると、多くの注文で配送コストを負担することになり、逆に高く設定しすぎると顧客にとって非現実的な条件となってしまいます。適切な条件設定には、平均客単価や商品構成の詳細な分析が必要です。
このパターンは、客単価向上の余地があるショップや、関連商品のクロスセル効果が期待できる商品構成のショップに適しています。
パターン5:一部商品のみ送料無料
特定の商品や商品カテゴリーのみ送料無料とするパターンです。戦略的な商品プロモーションと収益性のバランスを取りながら、顧客にメリットを提供できる柔軟な設定方法です。
このパターンのメリットは、重点的に販売したい商品を効果的にプロモーションできることです。新商品、在庫過多商品、利益率の高い商品などを送料無料対象にすることで、顧客の購買行動を狙った方向に誘導できます。たとえば、アパレルショップで新作ジャケットの売上を伸ばしたい場合、そのアイテムのみ期間限定で送料無料にすることで、注目度と売上の向上が期待できます。
また、商品の特性に応じた柔軟な対応が可能になります。利益率が高く送料を吸収できる商品は送料無料にし、利益率が低い商品は通常の送料設定にするといった、商品特性に応じた戦略的な価格設定ができます。この方法により、全体的な収益性を保ちながら、部分的に競争力の高い価格設定を実現できます。
顧客にとっても、お得感のある商品を選択する楽しみが生まれ、ショッピング体験の向上につながります。送料無料商品と通常商品を組み合わせることで、賢い買い物をしている満足感を得られます。
デメリットとしては、商品選択に制約が生じることで顧客満足度が低下する可能性があります。本当に欲しい商品が送料無料対象外の場合、顧客は不公平感を感じるかもしれません。また、送料無料商品に集中して売上が偏ると、商品構成のバランスが崩れるリスクもあります。
運営面では、どの商品を送料無料対象にするかの判断が継続的に必要になり、商品管理の複雑さが増します。また、送料無料対象商品の変更時には、顧客への十分な告知と説明が必要になります。
このパターンは、多様な商品ラインナップを持ち、戦略的な商品プロモーションを重視するショップに適しています。特に、季節性のある商品や在庫回転を重視する商品構成の場合に効果的です。
パターン6:期間限定の送料無料
特定の期間中のみ送料無料を実施するパターンです。キャンペーンツールとして活用することで、短期間での売上向上と新規顧客獲得を狙える効果的な手法です。
このパターンの最大のメリットは、キャンペーン効果による売上の急激な向上が期待できることです。セール期間、新商品発売記念、記念日イベントなどと組み合わせることで、顧客の購買意欲を大幅に刺激できます。たとえば、年末年始の繁忙期に「12月25日から1月7日まで全品送料無料」キャンペーンを実施することで、通常時の2倍から3倍の注文数を獲得することも可能です。
新規顧客の獲得効果も高く、普段は送料を理由に購入を躊躇していた潜在顧客にアプローチできます。期間限定という緊急性が購買行動を促進し、初回購入のハードルを下げる効果があります。また、既存顧客に対してもまとめ買いのインセンティブとなり、客単価向上が期待できます。
競合対策としても有効で、他社のキャンペーンに対抗した施策として機動的に実施できます。市場環境の変化に応じて柔軟に対応できる点は、期間限定施策の大きな利点です。
一方で、デメリットとしては期間中の配送コスト負担により利益率が大幅に低下することが挙げられます。特に注文が集中した場合、想定以上の配送費負担が発生するリスクがあります。また、キャンペーン終了後の反動により、通常時の売上が一時的に減少する可能性もあります。
顧客の期待値管理も重要な課題となります。頻繁に送料無料キャンペーンを実施すると、顧客が通常価格での購入を避ける傾向が生まれ、キャンペーン依存の事業構造になってしまうリスクがあります。
このパターンは、季節性のある商品を扱うショップや、新規顧客獲得を重視する成長段階のECサイトに適しています。また、在庫処分や新商品プロモーションなど、特定の目的がある場合にも効果的です。
パターン7:全品送料無料
すべての商品について送料を無料とするパターンです。顧客にとって最も分かりやすく魅力的な設定ですが、事業者にとっては配送コストの完全な内部化が必要になります。
このパターンの最大のメリットは、購入決定における送料の心理的ハードルを完全に排除できることです。顧客は送料を気にすることなく、純粋に商品価値だけで購入判断を行えるため、コンバージョン率の大幅な向上が期待できます。特に低単価商品や複数商品の購入において、この効果は顕著に現れます。
また、シンプルで分かりやすい料金体系により、顧客体験が大幅に改善されます。商品価格がそのまま支払金額となるため、購入プロセスがスムーズになり、カート離脱率の低下も期待できます。マーケティング面でも「送料無料」という明確なメリットを前面に打ち出すことができ、競合との差別化要因として活用できます。
リピート購入促進効果も高く、一度利用した顧客が継続して利用する可能性が高まります。送料負担がないことで、小額商品でも気軽に購入できる環境を提供でき、購入頻度の向上が期待できます。
一方で、最大のデメリットは配送コストの完全な内部化により利益率が圧迫されることです。すべての配送費を商品価格に転嫁する必要があるため、商品価格が割高に見える可能性があります。特に高額商品の場合、送料分の上乗せが明確に認識されやすく、価格競争力に影響する可能性があります。
また、配送先による実費の差を商品価格で調整することが困難になります。遠距離配送の多い顧客構成では、配送コスト負担が想定以上に大きくなるリスクがあります。さらに、返品時の配送費負担や、配送事故時のコスト負担など、運営面でのリスクも増加します。
このパターンは、十分な利益率を確保できる高付加価値商品を扱うショップや、大規模な物流ネットワークを持つ事業者に適しています。また、顧客獲得を最優先とする成長段階のECサイトでも戦略的に採用される場合があります。
| 送料設定パターン | メリット | デメリット | 適用場面 |
|---|---|---|---|
| 全国一律送料 | シンプル、地域格差なし | 配送コスト差を反映できない | 小型商品、全国展開重視 |
| 地域別送料 | 実費に応じた公平設定 | 複雑、遠距離顧客の負担大 | 重量商品、地域集中型 |
| 商品・重量別送料 | 最適な配送方法選択可能 | 管理複雑、顧客の理解困難 | 多様な商品構成 |
| 購入金額別送料 | 客単価向上効果 | 低額購入者の負担大 | クロスセル効果期待 |
| 一部商品送料無料 | 戦略的プロモーション | 商品選択の制約 | 戦略商品重視 |
| 期間限定送料無料 | キャンペーン効果大 | 利益率圧迫、反動リスク | 季節商品、新規獲得 |
| 全品送料無料 | 最高の顧客体験 | 配送コスト完全内部化 | 高付加価値商品 |
「送料無料」は本当に得?売上アップに繋がる仕組みと導入の判断基準

送料無料は顧客にとって魅力的な施策ですが、事業者にとっては慎重な検討が必要な戦略です。ここでは送料無料が売上に与える影響と、導入すべきかどうかの判断基準について詳しく解説します。
ネットショップが送料無料を実現できる仕組みとは?
送料無料を実現するためには、配送コストを他の方法で回収する仕組みが必要です。最も一般的な方法は商品価格への転嫁で、送料相当額を商品価格に上乗せすることで実質的な送料回収を行います。
商品価格への転嫁では、平均的な配送費を算出して全商品に一定割合を上乗せする方法が一般的です。たとえば、平均配送費が600円で、平均客単価が4,000円の場合、15%の価格上乗せにより送料無料を実現できます。ただし、この方法では単価の低い商品ほど送料の占める割合が高くなるため、商品ごとの調整が必要になる場合があります。
別の方法として、利益率の高い商品で配送費を吸収する方法があります。商品構成の中で特に利益率が高いアイテムがある場合、そのマージンを活用して配送費をカバーします。たとえば、オリジナル商品や独占販売商品などの高利益率商品があるショップでは、この方法が効果的です。
物流効率化による配送コスト削減も重要な要素です。配送業者との大口契約による料金削減、梱包の最適化によるサイズダウン、発送拠点の戦略的配置による配送距離短縮など、様々な方法で配送コストそのものを削減できれば、送料無料の実現が容易になります。
大手ECサイトでは、年会費制の送料無料サービスも採用されています。Amazonプライムのように年会費を徴収することで、頻繁に利用する顧客から継続的に配送費を回収し、利用頻度の低い顧客には実質的に送料を負担してもらう仕組みです。この方法では、顧客の利用パターンによって実質的な送料負担が変わるため、ヘビーユーザーほどお得になる設計になっています。
また、送料無料の条件を設定することで、客単価向上により配送効率を改善する方法もあります。「5,000円以上購入で送料無料」のような条件設定により、顧客により多くの商品を購入してもらい、一回の配送でより多くの売上を獲得することで、配送費の負担を軽減します。
赤字にならない!送料無料の損益分岐点の考え方と計算方法
送料無料を導入する際は、事業の収益性を維持するための損益分岐点を正確に把握することが重要です。適切な損益分岐点の計算により、送料無料が事業にプラスかマイナスかを客観的に判断できます。
基本的な損益分岐点計算では、まず現在の平均配送費と平均客単価を把握します。たとえば、平均配送費800円、平均客単価3,500円、粗利率40%のショップの場合、現在の平均粗利は1,400円(3,500円×40%)から配送費800円を引いた600円となります。送料無料にする場合、最低でもこの600円以上の粗利を確保する必要があります。
送料無料条件の最低購入金額は、「必要粗利額÷粗利率」で計算できます。前述の例では、800円÷40%=2,000円が最低条件となります。しかし、これは配送費をちょうど回収できる金額であり、実際には運営費や利益を考慮してより高い金額設定が必要です。
客単価向上効果も考慮する必要があります。送料無料により平均客単価が20%向上すると仮定すると、新しい平均客単価は4,200円(3,500円×1.2)となり、粗利は1,680円(4,200円×40%)から配送費800円を引いた880円となります。これは現在の粗利600円より280円多く、送料無料により実質的な利益向上が実現できることになります。
コンバージョン率の変化も重要な要素です。送料無料によりコンバージョン率が30%向上した場合、同じ広告費でより多くの注文を獲得でき、一件あたりの顧客獲得コストが削減されます。この効果も損益計算に含める必要があります。
季節変動やキャンペーン効果による注文数の変動も考慮すべき要素です。繁忙期には配送費負担が想定以上に大きくなる可能性があるため、年間を通じた平均的な収益性で判断することが重要です。
実際の計算例として、月間1,000件の注文があるショップで送料無料を導入する場合を考えてみます。現在の状況:平均客単価3,500円、配送費800円、粗利率40%、月間売上350万円、月間粗利140万円、月間配送費80万円、実質月間利益60万円。送料無料導入後の予測:平均客単価4,200円(20%向上)、注文数1,200件(コンバージョン率20%向上)、月間売上504万円、月間粗利201.6万円、月間配送費96万円(注文数増加により増加)、実質月間利益105.6万円。この例では、送料無料により月間利益が45.6万円向上することになります。
顧客の購買意欲を高める「送料無料」の効果的な見せ方
送料無料を導入しても、その効果を最大化するためには効果的な見せ方と伝え方が重要です。顧客の心理的な購買ハードルを下げる演出により、送料無料の効果を最大限に引き出すことができます。
商品ページでの送料無料の表示方法は、顧客の購買決定に大きく影響します。商品価格の近くに「送料無料」と明記することで、顧客が総費用を瞬時に把握できるようにします。特に効果的なのは、商品価格の下に「送料込み」や「全国送料無料」と表示することで、追加費用がないことを明確に示す方法です。
条件付き送料無料の場合は、達成までの金額を動的に表示することで購買意欲を刺激できます。「あと1,200円お買い上げで送料無料」のように、現在のカート金額と送料無料条件の差額をリアルタイムで表示する機能は、追加購入を促す効果が高いです。プログレスバーやメーターを使用して視覚的に表現することで、より効果的な誘導が可能になります。
送料無料商品の特別感を演出することも重要です。「送料無料」のアイコンやバッジを商品画像に重ねて表示したり、商品一覧ページで送料無料商品を優先的に表示したりすることで、顧客の注目を集めることができます。また、「期間限定送料無料」や「会員様限定送料無料」のように、限定性を強調することで緊急性と特別感を創出できます。
比較表現を使用した見せ方も効果的です。「通常送料800円→今なら送料無料!」のように、節約できる金額を明示することで、お得感を強調できます。また、競合他社との比較で「他社は送料がかかりますが、当店は送料無料です」といった表現も、差別化要因として訴求できます。
メールマーケティングでの送料無料活用も重要です。カート放棄者に対して「送料無料でお届けします」というリマインドメールを送信したり、会員向けに「今だけ送料無料」のキャンペーン告知を行ったりすることで、再購入を促進できます。
SNSやブログでの情報発信では、送料無料の価値を具体的に説明することが効果的です。「送料800円が無料になるので、その分でもう一つ商品が買えます」のように、節約効果を分かりやすく表現することで、フォロワーの関心を引くことができます。
また、送料無料の背景にある企業努力を適度にアピールすることで、顧客の信頼度向上にもつながります。「お客様により良いサービスを提供するため、送料無料を実現しました」といったメッセージにより、顧客との関係性を深めることができます。
まだコストを削減できる!ネットショップの送料を安く抑える4つのコツ

送料設定を最適化した後も、さらなるコスト削減の余地は多く存在します。ここでは実践的な送料削減のコツを4つご紹介し、利益率向上と顧客満足度の両立を実現する方法を詳しく解説します。
コツ1:配送業者と法人・個人事業主契約を結び料金交渉する
個人の定価配送から事業者契約への移行は、送料削減の最も効果的な方法の一つです。配送業者との法人契約により、20%から40%の料金削減が期待できます。
まず、配送実績をまとめて交渉材料を準備することが重要です。月間の配送件数、平均荷物サイズ、配送エリアの分布、年間の配送量予測などのデータを整理し、配送業者に対して具体的な取引規模を提示します。たとえば、「月間200件、年間2,400件の配送予定で、60サイズが70%、80サイズが30%の構成」といった具体的な情報を用意することで、業者側も適切な料金を提案しやすくなります。
複数の配送業者から見積もりを取得することで、競争原理を働かせることができます。ヤマト運輸、佐川急便、日本郵便の主要3社に加えて、地域密着型の配送業者も含めて比較検討することをお勧めします。特に地域限定の業者では、特定エリアで非常に競争力のある料金を提示される場合があります。
契約交渉では、料金だけでなくサービス内容も重要な要素です。集荷サービスの無料提供、梱包資材の提供、配送状況の詳細な報告システム、返品対応の充実など、総合的なサービス価値で判断することが重要です。単純に料金が安いだけでなく、顧客満足度に影響するサービス品質も考慮する必要があります。
契約後も定期的な見直しが重要です。配送実績が増加した場合や、配送パターンが変化した場合は、更なる料金改善の交渉が可能になります。年に一度は配送実績を基に料金見直しの相談を行い、事業成長に応じた条件改善を図ることをお勧めします。
また、支払い条件の交渉も重要な要素です。月末締め翌月末払いなどの支払いサイトを確保することで、キャッシュフローの改善にもつながります。特に成長期のECサイトでは、資金繰りの改善は事業運営において非常に重要です。
コツ2:梱包資材のサイズや種類を見直して配送サイズを最適化する
適切な梱包により配送サイズを最適化することで、大幅な送料削減が可能です。梱包の見直しにより平均配送サイズを一回り小さくできれば、1件あたり100円から200円の削減効果が期待できます。
まず、現在の梱包状況を詳細に分析することから始めます。商品サイズに対する梱包後サイズの比率、使用している緩衝材の種類と量、空きスペースの割合などを測定し、改善の余地を特定します。多くのショップでは、必要以上に大きな箱を使用していたり、過剰な緩衝材を使用していたりするケースが見られます。
商品に最適なサイズの梱包資材を用意することが重要です。複数の箱サイズを用意し、商品に応じて最小サイズを選択できるようにします。たとえば、60サイズ、80サイズ、100サイズの箱を常備し、商品に応じて適切なサイズを選択することで、平均的な配送サイズを削減できます。また、薄型商品には封筒型の梱包材を使用することで、さらなるサイズダウンが可能です。
緩衝材の見直しも効果的です。従来の発泡スチロールやエアパッキンに代えて、薄型の緩衝材や空気入り緩衝材を使用することで、梱包サイズを大幅に削減できます。特に書籍や化粧品など、それほど衝撃に弱くない商品では、最小限の緩衝材で十分な保護が可能です。
複数商品の同梱最適化も重要な要素です。商品の形状や重量を考慮した効率的な組み合わせにより、複数商品を一つの箱に収める際のサイズを最小限に抑えることができます。パズルのように商品を配置することで、予想以上にコンパクトな梱包が実現できる場合があります。
梱包作業の標準化により、担当者による梱包サイズのばらつきを防ぐことができます。商品別の梱包マニュアルを作成し、最適な梱包方法を文書化することで、常に効率的な梱包が実現できます。特に複数のスタッフが梱包作業に携わる場合、標準化は非常に重要です。
さらに、梱包資材のコスト削減も並行して検討すべき要素です。大口購入による単価削減、リサイクル可能な材料の使用、環境に配慮した材料への変更など、梱包コスト削減と環境負荷軽減を両立させることで、総合的なコスト効率を向上させることができます。
コツ3:発送代行サービスを利用して物流コスト全体を抑える
発送代行サービス(フルフィルメントサービス)の活用は、特に成長期のECサイトにとって大幅なコスト削減と業務効率化を実現する有効な手段です。専門業者の物流ノウハウとスケールメリットを活用することで、自社運営では実現困難なコスト効率を達成できます。
発送代行サービスの最大のメリットは、配送業者との大口契約によるスケールメリットを享受できることです。代行業者は多数のクライアントの荷物をまとめて配送業者と契約するため、個別契約では実現不可能な大幅割引料金を適用できます。たとえば、月間50件程度の小規模ショップでも、代行業者を通じて月間数万件規模の料金体系を利用できる場合があります。
在庫管理の効率化も重要なメリットです。代行業者の倉庫で在庫を一元管理することで、自社での在庫スペース確保が不要になり、賃料や光熱費などの固定費を削減できます。また、専門的な在庫管理システムにより、適正在庫の維持と欠品リスクの軽減が可能になります。
人件費の削減効果も見逃せません。梱包・発送作業に従事するスタッフの人件費、作業ミスによる損失、繁忙期の人員確保コストなどを総合すると、代行サービスの利用料と比較して大幅なコスト削減になる場合が多いです。特に繁忙期と閑散期の波が大きい事業では、固定人件費の変動費化により収益性が大幅に改善されます。
代行業者選定では、料金だけでなくサービス品質も重要な判断基準です。梱包の丁寧さ、配送スピード、在庫管理の正確性、顧客対応の質などを総合的に評価する必要があります。また、システム連携の容易さも重要で、既存のECサイトとの自動連携が可能な業者を選ぶことで、運営効率が大幅に向上します。
コスト構造の透明性も確認すべき要素です。基本料金、保管料、作業料、システム利用料などが明確に分かれており、将来的な事業拡大に応じた料金体系が理解しやすい業者を選ぶことをお勧めします。隠れた費用や想定外の追加料金がないよう、契約前に詳細な確認が必要です。
コツ4:複数の配送サービスを条件に応じて使い分ける
商品特性や配送条件に応じて複数の配送サービスを使い分けることで、最適なコストパフォーマンスを実現できます。一つの配送業者・サービスにこだわらず、柔軟な使い分けにより総配送コストを最小化することが重要です。
サイズ・重量による使い分けが最も基本的な戦略です。小型軽量商品には日本郵便のクリックポストやレターパック、中型商品には各社の宅急便、大型商品には専門の大型配送サービスといった具合に、商品特性に最適なサービスを選択します。たとえば、厚さ3cm以内の商品であればクリックポスト(185円)、それ以外は宅急便(地域により異なるが600円~)といった使い分けにより、小型商品の配送コストを大幅に削減できます。
配送先地域による使い分けも効果的です。近距離配送では地域密着型の配送業者が安価な場合があり、遠距離配送では大手業者の方が効率的な場合があります。また、離島や山間部など特殊な配送先では、専門的なサービスを持つ業者を選択することで、確実な配送と適正なコストを両立できます。
配送スピードの要求レベルに応じた使い分けも重要です。通常配送で問題ない注文には標準サービスを、急ぎの注文には速達サービスを、時間に余裕がある注文には低価格のエコノミーサービスを使用することで、コストと顧客満足度のバランスを最適化できます。
商品価値による使い分けも検討すべき要素です。高額商品や壊れやすい商品には保険付きサービスや高品質な配送業者を選択し、一般的な商品には標準的なサービスを使用することで、リスク管理とコスト効率を両立できます。
複数サービスの使い分けを効率的に行うためには、自動判定システムの導入が有効です。注文内容(商品サイズ、重量、配送先、顧客の希望など)を基に最適な配送サービスを自動選択するシステムにより、人的ミスを防ぎながら最適化を実現できます。
また、配送実績の定期的な分析により、使い分けルールの継続的な改善が可能になります。各サービスの利用実績、コスト効率、顧客満足度を定期的に評価し、より効率的な使い分けルールに更新していくことで、長期的なコスト最適化を実現できます。
配送業者との関係性も考慮する必要があります。複数業者を使い分けることで一つの業者への依存度は下がりますが、各業者との取引量が分散することで個別の料金交渉力が弱くなる可能性もあります。このバランスを考慮しながら、最適な配送戦略を構築することが重要です。
送料設定で失敗しないための重要チェックポイント
送料設定を実装する際は、法的要件や顧客対応の観点から重要なチェックポイントがあります。これらを適切に対応することで、トラブルを未然に防ぎ、信頼性の高いECサイト運営を実現できます。
特定商取引法に基づく表記を必ず記載する
ECサイトにおける送料表記は、特定商取引法により厳格に規定されており、適切な表記を行わない場合は法的な問題となる可能性があります。送料に関する必要な情報を正確かつ分かりやすく表示することが法的義務となっています。
特定商取引法では、「代金以外に必要な料金」として送料の表記が義務付けられています。具体的には、送料の金額、計算方法、支払い時期、支払い方法について明確に記載する必要があります。たとえば、「全国一律送料800円(税込)、商品代金と合わせてお支払いいただきます」といった具体的な表記が求められます。
地域別送料を設定している場合は、すべての地域の料金を明示する必要があります。「本州:600円、四国・九州:700円、北海道・沖縄:1,000円、離島:別途お見積もり」のように、顧客が事前に正確な送料を把握できる情報を提供することが重要です。離島や一部地域で別途料金が発生する場合も、その旨を明確に記載する必要があります。
送料無料の条件がある場合も、その条件を明確に表記することが重要です。「5,000円以上のお買い上げで送料無料(一部地域を除く)」のように、適用条件と例外事項を分かりやすく説明する必要があります。また、期間限定の送料無料キャンペーンの場合は、実施期間も明記することが求められます。
複数の配送方法を提供している場合は、それぞれの料金と特徴を表記する必要があります。「通常配送:600円(お届けまで2-3日)、速達配送:1,200円(翌日お届け)」といった具合に、顧客が適切な選択をできる情報を提供することが重要です。
特定商取引法に基づく表記ページは、サイト内から容易にアクセスできる場所に設置し、定期的に内容を更新することが必要です。送料設定を変更した場合は、速やかに表記内容も更新し、顧客に対して事前に十分な告知を行うことが重要です。
お客様に分かりやすい送料案内ページを用意する
法的要件を満たすだけでなく、顧客にとって理解しやすい送料案内を提供することで、購入時の不安を解消し、顧客満足度を向上させることができます。分かりやすい案内により、送料に関する問い合わせも削減できます。
送料案内ページでは、視覚的に分かりやすい表や図を使用することが効果的です。地域別送料の場合は、日本地図を使用して各地域を色分けし、対応する送料を表示することで、直感的に理解できる案内が可能になります。また、よくある注文パターンでの送料例を示すことで、顧客が自分の状況に当てはめて理解しやすくなります。
送料計算のシミュレーション機能を提供することも有効です。郵便番号や都道府県を入力することで、自動的に送料が表示される機能により、顧客は購入前に正確な送料を把握できます。特に複雑な送料体系を採用している場合、このような機能は顧客の利便性を大幅に向上させます。
よくある質問(FAQ)形式で送料に関する疑問に答えることも重要です。「複数商品を注文した場合の送料は?」「返品時の送料はどうなる?」「配送日時の指定はできる?」といった、顧客からよく寄せられる質問に対する回答を用意することで、顧客の不安を事前に解消できます。
配送方法の比較表も有効な情報提供方法です。配送業者、配送日数、料金、追跡サービスの有無、保険の有無などを表形式で比較表示することで、顧客が自分のニーズに最適な配送方法を選択できるようになります。
送料案内ページは、購入プロセスの複数の段階からアクセスできるようにすることが重要です。商品ページ、カートページ、決済ページのそれぞれから送料案内にリンクを設置し、顧客がいつでも送料情報を確認できる環境を整えることで、購入時の不安を解消できます。
離島や一部地域への対応方針を明確にしておく
離島や山間部などの特殊な配送先への対応方針を事前に明確にしておくことで、注文後のトラブルや顧客とのクレームを防止できます。これらの地域では通常の配送サービスが利用できない場合があるため、特別な対応が必要になります。
まず、自社で配送可能な地域と不可能な地域を明確に定義することが重要です。配送業者の配送エリア情報を基に、対応可能地域のリストを作成し、顧客が注文前に確認できるようにします。特に、離島の中でも配送可能な島と不可能な島がある場合は、詳細なリストの作成が必要です。
配送不可地域への対応方針も決めておく必要があります。完全に配送を断るのか、代替案(最寄りの配送可能地域への配送、顧客による引き取りなど)を提案するのかを事前に決定し、顧客に案内できるようにします。また、配送可能であっても追加料金が発生する地域については、その料金体系を明確にすることが重要です。
離島配送の特別料金については、配送業者と事前に確認し、正確な料金を顧客に案内できるようにします。多くの場合、離島配送には通常料金に加えて特別料金が発生するため、これを事前に顧客に伝えることで、注文後のトラブルを防止できます。
配送日数についても特別な案内が必要です。離島や山間部では通常より配送に時間がかかることが多いため、「通常2-3日のところ、離島・山間部は4-7日程度かかる場合があります」といった具体的な案内を提供することが重要です。
注文システムでの対応も重要な要素です。郵便番号による自動判定により、特殊配送地域の注文を識別し、適切な送料計算や注意事項の表示を行うシステムを構築することで、運営効率と顧客満足度の両立が可能になります。
顧客への事前連絡体制も整備しておくことが重要です。特殊配送地域への注文があった場合の確認フローを決めておき、配送可能性や追加料金について顧客に事前連絡を行う体制を構築します。これにより、顧客との認識齟齬を防ぎ、スムーズな取引を実現できます。
まとめ:自社に最適な送料設定を見つけてECサイトの売上を伸ばそう

適切な送料設定は、ECサイトの売上向上と顧客満足度向上を両立させる重要な戦略要素です。本記事で解説した内容を参考に、自社の事業特性と顧客ニーズに最適な送料設定を見つけ、継続的な改善を行っていくことが成功への鍵となります。
送料設定の成功は、一度の設定で完了するものではありません。市場環境の変化、顧客ニーズの変動、競合状況の変化に応じて、柔軟に見直しを行うことが重要です。定期的に送料設定の効果を測定し、売上データ、顧客満足度、利益率などの指標を総合的に評価しながら、最適化を継続していきましょう。
また、送料設定は単独で考えるのではなく、商品価格、マーケティング戦略、顧客サービス戦略との整合性を保ちながら検討することが重要です。顧客にとって魅力的で、事業者にとって持続可能な送料設定を実現することで、長期的な事業成長を支える基盤を構築できます。
今回ご紹介した5つのステップ、7つのパターン、4つのコツを参考に、ぜひ自社に最適な送料設定を見つけて、ECサイトの更なる発展を実現してください。適切な送料設定により、顧客満足度の向上と事業収益の拡大を同時に達成し、競争力の高いECサイト運営を目指しましょう。
100%プライバシーを保証いたします